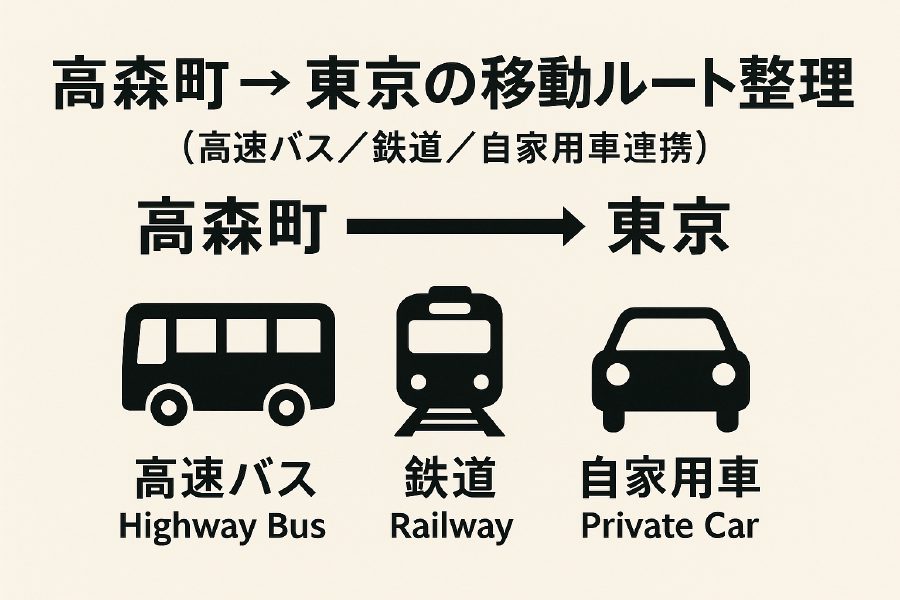はじめに
最近、自宅で冷凍庫をもう一度導入しました。いわゆるセカンド冷凍庫です。なかなか便利に使っています。ここでは、それを導入した背景と、どんなふうに運用しているかをメモしておきます。
選んだ冷凍庫について
ツインバードのHF-E916 と言う機種です。色は白にしました。
https://store.twinbird.jp/products/hfe916
選んだ理由は
省エネ性能がくランニングコストが抑えられる
容量がある程度大きいこと
急速冷凍モードがあること
霜取りが不要なファン式であること
でした。他のメーカのものも検討しましたが、我が家にはこれがベスト。ただ、省エネの分だけ断熱層が厚めで、サイズもセカンド冷凍庫としてはかなり大型になりますので慎重に選んだ方がいいかもです。
また、調べているときに気付いたのは、冷蔵庫、特に冷凍庫は「容量と消費電力が比例しない」ということです。容量が大きいと消費電力が大きくなりそうと言うのが普通の感覚。私もそのイメージだったのですが、調べると全然そうじゃない。
むしろ、一人暮らし向けなどの小型タイプの方が、ファミリー向けの大型タイプより消費電力が大きいとかそういうことが普通にあります。それも2年~3年使えば元が取れるような価格差で済むレベルの価格差しかないとかです。この冷凍庫もそうでした。結構容量が大きいのですが、恐らく数年で価格差が吸収出来るレベルで消費電力が少なかったです。選ばれる方はそこをチェックポイントにするといいかもですね。
冷凍庫を購入したきっかけ
まず、冷凍庫を購入したきっかけです。病気をしてから自分自身のケアにある程度時間が必要になってきました。ケアをちゃんとやらないと結局色々な事が破綻すると言う事が分かってきたのです。
さらに、仕事と介護や生活を両立しながら、クオリティを落とさず暮らしていく、やるべきことに時間を使えるようにしたいと考えました。
そこで色々な事を考えてやっていますが、その中で、作ったものをストックしておくなどして時間を効率化できるのではないかと考えて導入しました。そのほかに、私が出社している時に、両親が簡単に調理して食べられるものをストックしておくということも意識しています。
買い出し頻度と賞味期限の課題
以前から、時間とお金の節約のため、週の中でできるだけ買い出し日を少なくし、週に1回または2回の買い出しで1週間分の食糧を確保する運用をしていました。しかし、次の買い出しまでの期間が少し空くと、どうしても賞味期限的に微妙な感じになります。日付的には切れてしまうものが結構出てきてしまいますし、実際にわるくなるもの、味がかなり落ちるものが出てきます。
最近の冷蔵庫は特に野菜室が工夫されていて性能が良く、私はメインの冷蔵室全体がチルド温度になるような低めに設定しているので、1週間程度であればある程度は持ちます。それでも、予定の変更で食材を使い切れないと残ってしまい、無駄になることがかなりの頻度で起きていました。そして、これを防ぐ為に管理工数がかかっていて、脳のリソースが割かれている感じがありました。
また、長く安定して保存するには、肉ならブロック肉(かたまり肉)で買うなどの工夫が必要です。魚も生は傷みやすいので避け、下処理してあるものを用意するといった地味な工夫が要ります。そこまでしても、もやしやなまこような足の速いものは、基本的に1週間持たせることはできません。
冷凍化という解決と学び
そこで、これらを解決するために、冷凍にすることにしました。当初の目的としては、冷凍庫を導入し、いろいろな食品をストックして買い出しの頻度を週1〜2回に抑えつつ、1週間暮らしていけることでした。さらに調べてみると、「野菜は丸のままではなく、用途に合わせて事前に加工してから冷凍するのが普通」ということが分かりました。冷凍食品メーカーのニチレイさんが監修されている本「ニチレイフーズの広報さんに教わる 食材の冷凍、これが正解です!」 を読んで勉強したのですが、水分が多く一般的には冷凍できないと思っていたもの(例えば大根)でも、丸ごとではなく用途に合わせてあらかじめ加工してから冷凍を徹底すれば、問題なく解凍できることが分かりました。
冷凍することの副次効果として、メニューで使用する形をあらかじめイメージし、そのサイズにカットしておけることも大きいです。当初は魚や肉を中心に、既存の冷凍食品を多く冷凍保存する予定でしたが、結果的に「自作の冷凍野菜」をたくさん作るようになってきています。
ラップ個包装の手間と真空パック導入
こちらの本では、冷凍保存の手順として「1個ずつラップで包む」作業が頻繁に出てきます。これは、空気に触れる面積を減らし品質劣化を防ぐためです。意図は理解できますが、私の冷凍庫導入の目的は「できるだけ時間を節約しつつ、生活の質を落とさず、野菜もちゃんと入った食事を出す」ことです。ひと手間のラップ作業を一つ一つやっていると、クオリティも時間効率的にも厳しいです。
そこで、冷凍庫に加えて真空パック機を導入しました。真空パックは空気を抜いて保存するので、酸化を防げます。実は冷凍との相性が非常に良くいのです。
単純に冷凍すると、0℃以下になり、仮定だとマイナス18度保存がデフォです。この状態では水分は凍っていても、塩分やたんぱく質、油などは凍りません。この状態でも空気に触れると酸化が進んでいきます。また温度変化によって水分が結晶化して出てしまい「冷凍焼け」という問題が発生します。これが冷凍食品の寿命の多くを決めます。
しかし、そこで真空にしてから冷凍すれば酸化と冷凍焼けの現任になる、空気をほぼシャットアウトできるのです。これで大きく長持ちします。さらに袋に野菜などを入れて真空にすれば、1個ずつラップで包むよりはるかに簡単に密閉でき、袋が中身に密着してくれるので扱いやすいです。熱で圧着されるため、内容物が出てくることもありません。
導入から約2ヶ月の運用メモ
カレー(常備菜)
まずカレーです。いつも冷凍のカレーを常備するようになりました。ジップロックコンテナの「2」サイズにおよそ200g入る容器を使い、一度に大量に作ったカレーを入れて、冷蔵庫の急冷モードをつかって粗熱を取った後に冷凍庫に移し、急速冷凍モードで凍らせます。カチカチの状態で保存できるので、時間がない時や、私が不在の時に父や母の食事として提供できます。カレーは牛肉ではなく、もっぱら鯖の水煮をつかったサバカレーにすることが多いです。これは我が家の好みでもありますが、塊肉は冷凍で食感が変わりやすく硬くなりがちで、その問題をサバカレーにすることで回避できるためです。たくさん作って食べ切ったら、またすぐ作るという形で、常備菜として用意しています。
お肉類(鶏もも肉)
お肉類で常備しているのは、鶏もも肉が一番多いです。相場は安くても100gあたり128円くらいですが、タイミングによっては98円で買えることもあります。その場合は「メガ盛り」で大量に買ってきます。従来は使い切れないこともありましたが、今は購入した鶏もも肉に、ミートソフター(隠し包丁を入れる剣山のような器具)で満遍なく穴をあけ、繊維をほぐして平たく伸ばします。この状態で袋に入れて真空パックし、冷凍します。非常に薄い鶏もも肉の冷凍プレートになるので、立てて保存できます。使う時は取り出し、あらかじめ分かっていれば冷蔵庫に移して解凍します。思いつきで今すぐ使いたい時は、水を張ったフライパンに袋のまま入れ、火はかけません。水の高い熱伝達率で急速に解凍できます。真空パックしてあるので、そのまま浸けてOKです。これで常に鶏もも肉がある状態になり、料理に悩まなくなりました。
また、あらかじめ唐揚げ用や照り焼き用の下味を付けて真空パック冷凍にしておくこともやり始めました、もう出しただけでほとんどできているので本当に簡単です。
魚(3人分の小分け)
魚も、購入したら一度に食べる量(我が家は父・母・私の3人暮らし)に合わせて3つに分けて袋に入れ冷凍するようになりました。
以前は「メガ盛り」のような大容量は扱いづらく手を出しませんでしたが、今は購入して、冷凍のまま3つに小分けし、真空パックして冷凍保存します。食べる時に取り出して、少し解凍して焼けばすぐ食べられます。スーパーで賞味期限が近く半額や割引のシールが貼られているものも積極的に購入し、冷凍して使うので、結構な節約になっていると思います。いわゆる食品ロスの軽減にもなってるんじゃないかと。
野菜(まとめ切りと常備)
肉・魚以外では、野菜を刻んで冷凍しています。大根はお味噌汁用、炒め物用などの形で切り分けます。一度に大量に切る時は往復式の電動調理器を使います。毎日の味噌汁程度の少量調理では、機材の出し入れと洗浄の方が時間がかかるので不向きですが、週末に時間を見つけて大量に切って冷凍保存するなら、十分に価値があります。例えば大根を2本丸ごと買ってきて、全部切って下ごしらえしておきます。同じ考え方で、ナスや小松菜なども冷凍できます。特に小松菜は夏は安いので、たくさん買ってカットして保存します。野菜炒めにも味噌汁にもさっと入れられます。小松菜は鉄分が豊富で、鉄分が不足しがちな我が家では必ず常備しています。野菜室でも持ちますが、冷凍なら葛藤した状態にできるので、使う時にそのまま出せるのが大きなメリットです。
きのこ(冷凍との相性)
私はきのこをよく食べますが、きのこと冷凍の相性が非常に良いです。しめじはバラされたもの、えのきはカットえのきを買ってきて、そのまま冷凍できます。食べ比べると、冷凍したきのこの方が出汁がよく出ておいしい感じがします。実際うまみ成分は増えているのだそう。少し柔らかくなる感じもあり、きのこは基本的に冷凍してから調理した方がおいしいかもしれません。なめこの味噌汁も明らかに増えました。なめこは足が速く、冷蔵では2〜3日しか持ちませんが、柄が切られた真空パックの状態のものなら、そのまま冷凍庫に入れて凍らせ、使う時は冷凍のまま味噌汁に入れられます。非常に便利で、最近は「楽しいなめこライフ」を過ごしています。
平日の時短効果:テレワーク中の昼食
こうした運用で、野菜の多くが冷凍できることに気づき、いろいろな時間の短縮ができています。時短効果で一番大きいのは、テレワーク中の昼食です。お昼ご飯は、私だけでなく家族の分も同時に作っています。例えば肉うどんを作る場合、豚の切り落とし肉はあらかじめ食べやすい大きさに切り、100gずつで冷凍しています。これを取り出してフライパンに入れ、解凍しながら炒めます。スライス済みの玉ねぎも冷凍してあり、必要量を取り出します。小松菜やキノコも気宇分で投入します。
これらは炒め物前提で冷凍しておけば、組織が壊れていて早く炒められます。時間的には、冷凍うどんを茹ている間に具を炒め上がる感じです。粉末のうどんスープで仕上げればできあがり。
以前は12:05に調理開始して12:30を少し過ぎる頃に昼食、という感じだったのが、今はおよそ10〜15分で、12:20くらいには食べ始められます。お昼安物10分は夜の1時間に相当する価値がある!・・・かもしれません。その時間でゆっくりご飯を食べ、落ち着いて介護をして、その後に皿洗いをしても、充分に余裕を持って午後の業務に戻れます。これは非常に大きいです。
真空パックの使い心地とコスト
導入した真空パック器
導入したのは、アスクワークスさんの PZ-290SE と言う真空パック器です。私はAmazonで買いました
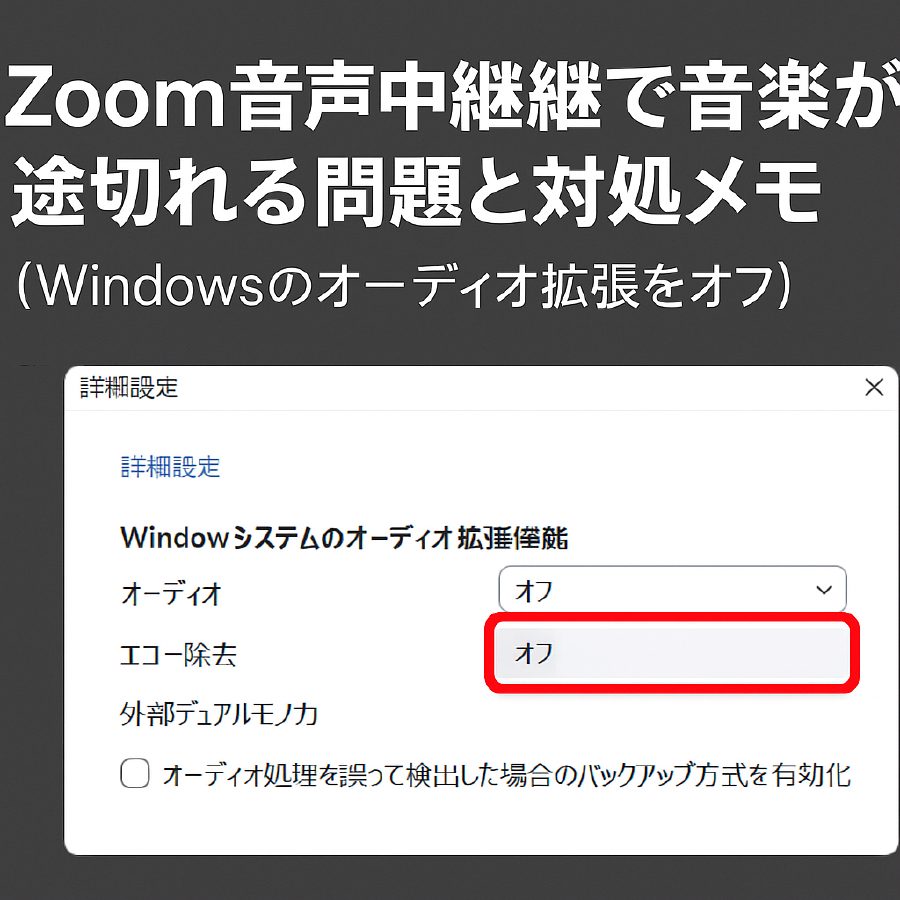
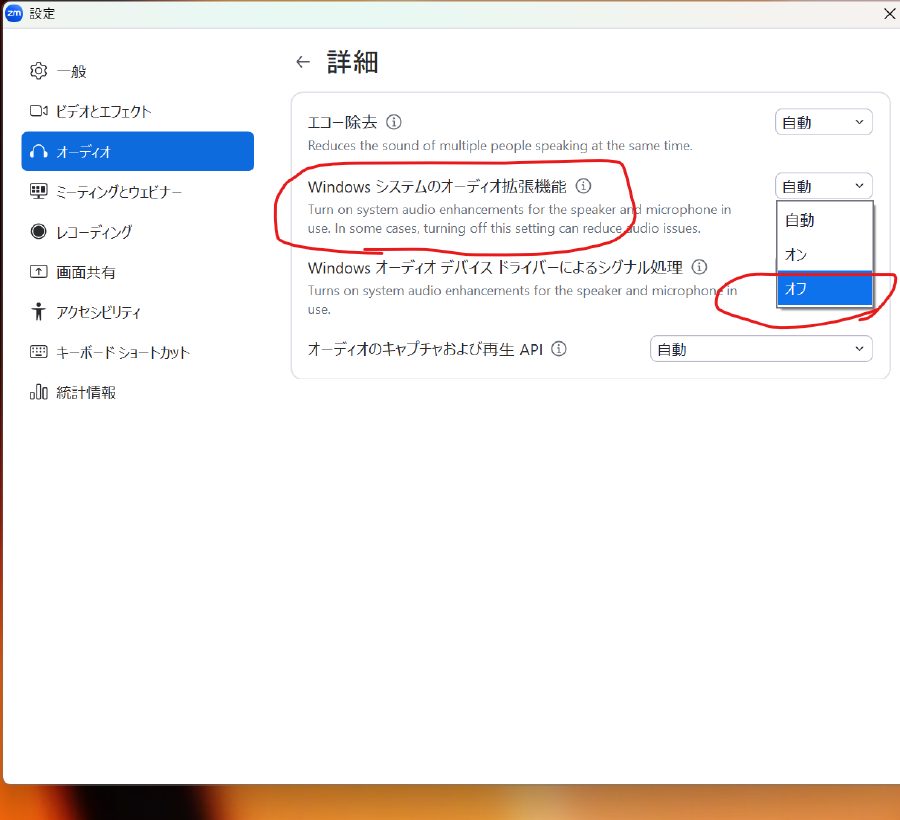
 マツヒデのノート
マツヒデのノート